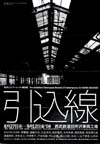●鉄の哲人
先日、以前から決めていたインタビューの為に、今年度から多摩美術大学の教授となられた多和圭三さんを訪ねた。そう、鉄を叩いて何十年、という日本を代表する「鉄」の作家のひとりである。八王子から大学直行のバスに揺られ、横浜へ向かう16号を20分程。丘の上に聳える天空都市のような大学キャンバスの最奥。整備された急斜面をゆっくり登り切ってやっと着く。久しぶりの再会ではあるが、多和さんの風貌は例の如く野を行く仏師のよう。出迎えてくれた姿はさらに冬の厚着で丸々となって、さらに迫力を増している。インタビューは多和氏の研究室でおよそ1時間。そして大学内を案内いただきながら見学。途中多くのどばた出身学生達に声をかけられたり、また発見したりとなんとも懐かしく、いい一日となった。
なんというか、世代的にも同じという親近感もあり、生きること、表現することの関係の視点が共感する。中身に関しては後日「インタビューコーナー」で詳しく。ご期待を!!
製作中作品の前で(多摩美金属棟にて)