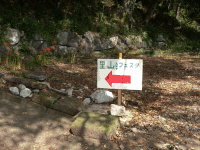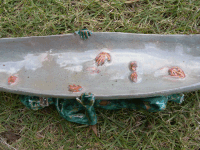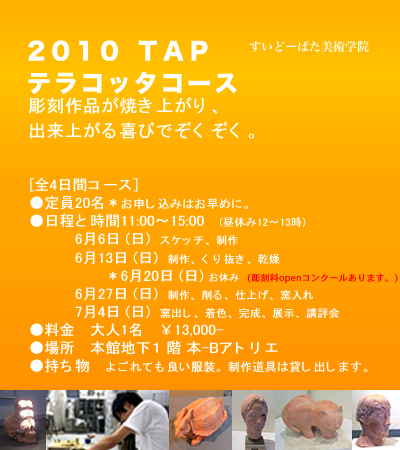●もてぎ里山アートフェスタへ!
スイカ電車(真岡鐵道)に乗って。
都心から一転、のんびりと時間が流れる栃木の茂木へ。

台風の後の快晴、最高の天気。
阿部さんの作品が展示されている野外展、『もてぎ里山アートフェスタ』に行ってきました!!
長旅でしたが作品はもちろんの事、展示会場の空気や土地、人を直に肌で感じられる事ができた、とても充実した1日でした。


展示会場は、城山公園。茂木城があったというだけあり、坂道が続きます。

いざなわれる様に作品が現れました。染め物の作品が空中に張られていて奇麗でした。

景色に目を向け新鮮な空気を満喫しながら、ゆっくりゆっくり坂道を上って行くと突如扉が!
そんな演出?思う大人な感想なんかを簡単に越えて、この扉に心はワクワク。
避けて通る事もできるけど、じんわり楽しみながら扉を通ってみたり。
非日常の世界へ気持ちごと持って行かれました!

この中に、焼き物で出来た作品があります。横には水が流れていて、野外展ならでは。焼き物で、この形か!?と、主張はしないけど妙に存在感のある作品でした。

脇の道のひっそりとした空気が漂う木陰に、何とも華奢な作品がありました。
線がとても奇麗で、重なりあって生まれる空間は透明感があり、目を引きました。

白い扉と山下に見える街の景色と青い空。
普段は、陶芸をやられている作家さん。そこに、このアートフェスタの面白さが見え隠れします。

漆作家さんの作品です。漆と色彩、中々普段目に出来ない貴重な作品との出会い!
そしてそして、ゆっくり山を登り、見えて来た阿部さんの作品。

座って見たり、作品の中へ立って見たり、触ってみたり、考えてみたり。
作品を見ながら、芝生の上でのんびり。
この大きな自然に囲まれながら、一人の人から作りだされた3日間しか存在しない空間を、どうやって自分は受け取るのか?その場に居るという事はどういう事なのか?
色々な事も考えながら、、
ただただ、言葉にできない素直に感じた思いを楽しみたいと作品を眺めていました。

作品への意思や作品の在り方などを伺うと、こう感じたのはこういう事だったのか!と、とても興味深い感動を覚えました。
おこがましいのですが、作品が自然や空間に、勝つ負けるといった事ではなく、とても見る事が楽しい空間でした。
陶芸、染め物、漆、など相手があっての作品を手がけておられる作家さん達が、そこ意外の立ち位置で作品を作る事。
野外での作品展開。
一人の脳の中では済まず予想外な事もたくさんあるであろう中、まさに普段はやれない事への挑戦。
違う時間軸で様々な生き方をしているメンバーが、同じ時間と場所を共有する。
そんな流れを含んだ作品が同時に展開される場所も、もてぎ里山アートフェスタならではだと思います。
自然の中で見せると言う事、またフェスタ自体の企画など、沸々と熱い思いを感じさせられる、刺激を受けながら楽しくもある、忘れられない1日でした。
作家とは?アートとは?
氷室 幸子