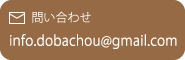「インタビュー企画第48弾」
2024全国公開議次コンクール特集
〜すいどーばた美術学院講師10名の採点講評コメント掲載〜
各講師から、今回の公開コンクールについての総評を書いてもらいました。
それぞれの言葉をしっかりと受け止め、今後の制作の参考にしてもらえればと思います。
文章が送られてきた順に掲載します。
すいどーばた美術学院 彫刻科夜間部講師 嶋田一輝
皆様お疲れ様でした。
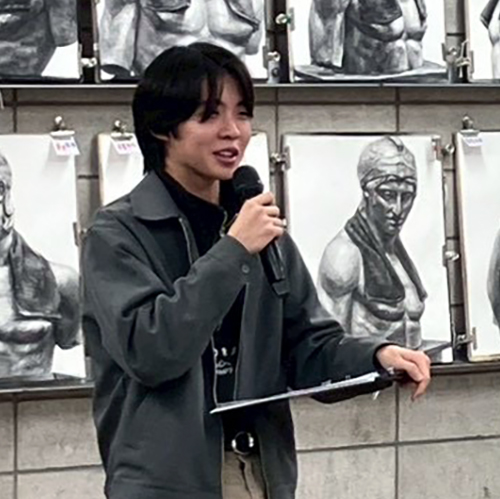
公開コンでは珍しく組み石膏。現役生にとっては「マルスだけでも大変なのにタオルまでかかってるのかよ!」とか思ったかもしれません。
タオルがかかったことで、精度が落ちていたり、全てを同じように触りすぎて、モチーフの状況が分かりにくい作品が多く目立ちました。
反対に、グレーのタオルと組み合わさることで質感や固有色の幅が出しやすいなと思えた人は絵面が作りやすかったと思います。
上位の作品はその辺りが無理なく伝わってきました。
これは経験値の差も大きいと思いますが、冷静に作戦を立てられたか否かの差でもあると思います。
モチーフに振り回され、手だけ動いていては出せる力も出せません、石膏単体でも組石膏でも、毎回全てを利用してください。
残り4ヶ月出来ることは沢山あります。頑張りましょう!
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 稲垣慎

総評です。皆様お疲れ様でした。私は概ね以下のような基準で採点をしました。
マルスは非常に体の厚みのある像ですので、動きやプロポーション、像を取り巻く空間は勿論の事、位置に関わらずこの厚みが正しく捉えられているかどうかを重点的に見ました。そして本課題にはモチーフとしてグレーの布が掛かっておりますので、厚みを出した先で固有色の差も画面の中に卒なく表現されている必要があります。
当落線上や僅差のものを順位付けする際には、短絡的な基準ではありますが、やはり顔の印象の良し悪しはどうしても目立ってきました。他に良い要素があったとしても顔面の印象に違和感があると良い評価を付けられませんでした。
一位の作品は、遠目だとモチーフを取り巻く空間が、近目だと力強い形が見えてきて、とても良い作品だと思います。顔の印象も良く色味も重厚で、作者のモチーフを見て感じた事や、大一番での気迫が伝わってくるように思います。
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部夜間部兼任講師 小野海
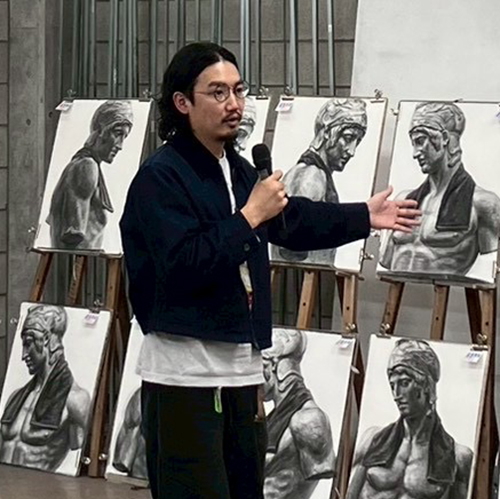
採点する側の心理をここにクドクド書き連ねても、描く側の皆さんにはまーったく関係のないことなので、皆さんと同じくデッサンを描く側の自分としてデッサンの話しを書こうと思います。
僕が生まれ育った神戸という土地は六甲山と瀬戸内海、両方に恵まれていて、小さい頃から山と海によく出かけてました。で、僕が思うにデッサンは登山に似てて、クロッキーは魚釣りに似てます。素描はその両方が合わさった感じです。全部話すと長くなるのでデッサンのことだけちょこっと書きます。
デッサンの何処が登山に似ているかと言うと、まず始める前に準備をするんですね、つまり計画を立てるわけです。どんな形の山なのか、どれくらい時間がかかるのか、登る前にイメージするわけです。プランがあるからスタート出来ます。それが不十分なのに登り始めるのは無謀です。いざ登り始めたら楽しむのみです。想像を超える景色が見れたり、空気や疲労を実感することで、その瞬間に感動できるわけです。もちろんただ進むだけではなく時には地図を確認して、進んでいる方向が合っているのか、自分がいまどの段階にいるのかを確認します。そして一歩ずつ着実に前に進み、無事に帰ってきます。
僕は登山が終わったあとは「勝った」という感情になります。デッサンも同じです。描けたら良いなではなく、描くのみです。そのために丁寧な観察と確認をすることが大切ですよね。もし完登できなければ落ちるだけです。
山に比べれば石膏像なんてちっちゃいですから、落ち着いて向き合えば必ず描けます、絶対描けます!
残り4ヶ月、たくさん勝負して自分に勝ってください!
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 田中綾子

公開コンクール、おつかれさまでした。
みなさんはジブリの「もののけ姫」を観たことはありますか?私はもののけ姫が大好きで、小学生だった頃に弟と一緒にVHSが擦り切れるくらい観ていました。
オープニングの壮大な音楽と霧がかった森が映るところからもう最高で、出てくる景色も全部良くて、モロや乙事主もカッコいいし、何度見ても「やっぱ最高だった〜」と思っていました。
そしてそこから20年ほど時間が経ち、数年前コロナによって閉鎖状態だった映画館の営業が再開した頃、ジブリ作品が映画館でリバイバル上映されました。これは絶対に観なければ!と、当然もののけ姫を観に行きました。
大好きだった作品を、大画面で、大音量で観られる喜びで、オープニングで大号泣しました。観る前から、一瞬も見逃すまいとは思っていましたが、そんなことを考えなくても映像と物語に引き込まれ、あっという間の2時間。
しかし最後の、アシタカが「共に生きよう」とサンに伝えるシーンを観た時、幼少期に観ていたときの感動とは違った感動が、ものすごい勢いで自分の中を通り抜けるような感覚がありました。
あれだけ繰り返し観ていた作品で、セリフも覚えているくらいだったのに、物語を本当に理解できたような気がしたのはこの瞬間でした。
初めて観た時から20数年経ち、自分自身も色々な経験をしたからこそ、深く物語を受け止められたのかなと思います。もしかしたら、これからまた10年20年経ってから観たら、もっと感動するのかもしれません。
長い長い前置きを失礼しました。
デッサンもよく、その日その時の感動を描こう、楽しんで描こうと言われます。
感動と一口に言っても、いろんな感動があります。新鮮じゃなくてもできると思うんですよね。経験を積んだからこそ、面白さに気がつけることもあります。
今回上位に食い込めなかったデッサンたちは「これをやらなきゃ」「これを守らなきゃ」に縛られて、モチーフに踏み込んだ上で表現できていないような気がしました。なんだか、習ったことをやるので精一杯でぎこちなくなってしまって、モチーフ本来の面白さを素直に画面に表現できていないような...
もちろんやらなきゃいけないことはたくさんあるけど、まずはカッコいい絵にしたい。正確に描かなければならないというのも、正確に捉えようとしなければモチーフのカッコ良さを取りこぼしてしまうからです。どんな経験値の人でも、そこを忘れずに取り組んでいってくれたらいいなぁと思っています。
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 阿部光成

採点会場に入った第一印象ですが、発色が良くなかったのが気になった。炭の扱いうんぬん以前の話、まずは描いた画面を人に見せる意識が欠けてはいけないね。
上位はそこそこのレベルだけど、中盤から下位はほとんど差を感じない!
これはチャンスだね〜少しの改善で大きく順位が駆け上がるよ!
その少しの改善は例えば台座にどうモチーフが乗っているかどうか?
実は台座とモチーフの関係や、今回首に掛けたタオルをどうプロポーションの精度に活かせるか?その少しの気付きで内容は大きく変わるんだよね。
採点の時、画面からキラメキを感じると、ささやかでも見逃せない魅力を感じるね。
その時何を感じるか(入力)。それをどう画面に描けるか(出力)。素描の基本姿勢を忘れないでね!
すいどーばた美術学院 彫刻科主任 小川寛之
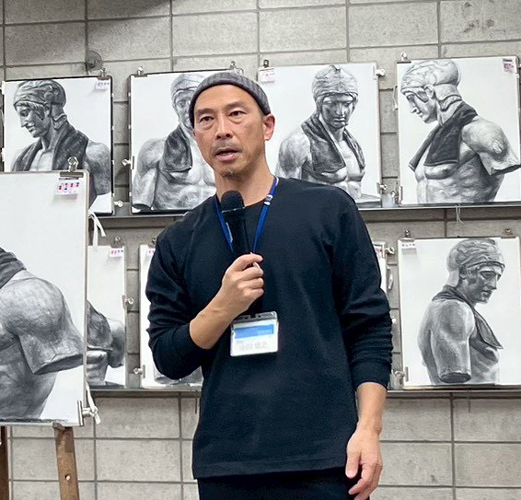
まず、142名という多くの彫刻を志す学生が集合した事に喜びを感じます。
今回、一位の作品は近年の公開コンの中でも安定した内容であったことと、二位の固有色を大事にしたお手本のような作品が見れてよかったです。
課題としては6位くらいから上位層の厚みと、合格数がもっと増えてなくてはいけません。
またB"層が多く、基礎力の強化が必要といった所でしょうか。
全体には、構造的な破綻もそうですが、木炭の扱いに強引さがありました。
今後、彫刻をしていく我々にとって、素材を操る感覚は最重要になっていきます。
たかが石膏デッサンであっても、炭の色味を充分に引き出して作品にしてください。
最後に皆さん、この世代でも彫刻界を盛り上げていくわけです。
良い感覚を育て、お互い頑張っていきましょう。
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 遠山蘭

皆さんお疲れ様でした!
今回は全体として、マルスのプロポーションが狂っているなあという印象が強かったです。...が、その反面上位のほうは説得力のある描写で、狂いを凌駕するような魅力で押し切っている絵が何点か並んだと思います。
総評として、皆さんにお伝えしたいことは一点『本番でいつもの実力を出せているかどうか?』です。
即興演奏を仕事にするジャズ奏者は、何が起こるかわからない何でもありな一度きりの"即興"だからこそ、毎日欠かさず基礎練習をするらしい。
私たちも、何が出題されるかわからない一度きりの試験のために、毎日基礎的なトレーニングをしていると考えて良いでしょう。
毎日の課題の出来栄えで一喜一憂もわかりますが、結論、どんなに毎日のトレーニングで良いものが出せたとしても、試験本番で実力を出せなければ全く意味がないということです。
プレ試験とも言える公開コンクールでいつもより結果が振るわなかった人は、何か取り組み方を改める必要があるかと思います。
一概にやり方や描き方を変えろという意味ではなく、まずは、心構えであったり自分の中の固定観念を見直すところから始めてみてください。
よく、コンクールや本番に良い波を持っていこうなどと言われますが、それはメンタルに効果的です。
自分自身は日々変わります。その自分に柔軟に対応すること。これも練習の一環と言えるでしょう。
試験当日に自信がないなんて言えません。内心どれだけ焦っていて自信がなくたって、揺るがない自信と覚悟を持ってやるしかありません。
その日のための練習だと自覚を持って今後の4ヶ月取り組んでいきましょう。
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 古賀悠悟

皆さんお疲れ様でした。
今後作品を作っていく上で、作る前だったりリサーチの際にドローイングを描いたりすることがあると思います。それが本来彫刻家がデッサンをする理由です。描くことでモチーフから学び、作品の見え方を平面の中で検討するということです。
全体を俯瞰した感想として、勢いとか熱意は感じるのですが、当たり前の事を当たり前にする冷静さがない作品が多いように感じました。
特に肩の入り方、頭部の入れ方がうまくいっていない作品が多く、その上から描いていってなんとかしようとしている作品が多く見受けられました。
B゜に入ってきても評価が割れている作品が今回多いように思いますが、それは一見よく見えていても、基礎の部分がまだ安定していないということだと思います。
一方上位層のデッサンには構図や動きに加え、絵としての見え方だったり、臨場感、モチーフのかっこよさが描けている作品が並んでいるかと思います。
いくら見やすくかっこいい炭を使えていても、構図が違えば、動きが違っていたらいい作品にはなりません。あと4ヶ月あります。冷静な観察力を磨いてください。
すいどーばた美術学院 彫刻科夜間部講師 小柳湧志

お疲れ様でした。
今回の全体的な印象としては、絵はカッコいいのですが「石膏デッサン」という括りの中だけで描いているものが多い印象で、単純なデッサン力を感じさせるものがもう少し見たかったなといった感じです。質の差・色の差を、もっと大切にしていきたいですね。
夜間部講師ですので、現役生へ向けて少しだけ、、
「上手くいかなかった」などと思うのではなく、これが今の実力なのだと受け止めるのも大切なことです。試験までは4ヶ月あります。最後まで諦めなかった人は、入試直前で爆発的に伸びる傾向があります。どんなにヘタクソでもいいので、しっかり受かると決め、食らいついてみてください。
なんせ大学に落ちたことがないというのは藝大受験においてある意味最強です。落ちたことがないからこそ湧いてくる自信、気合い、無尽蔵のやる気をとことん燃やしてください!
そして浪人生。 同じことをなぞると時間が勿体ないので、変化を加えながら残りの4ヶ月を過ごせるように頑張ってください。鮮度は全ての上を行くと思います。
すいどーばた美術学院 彫刻科昼間部講師 小原壮太
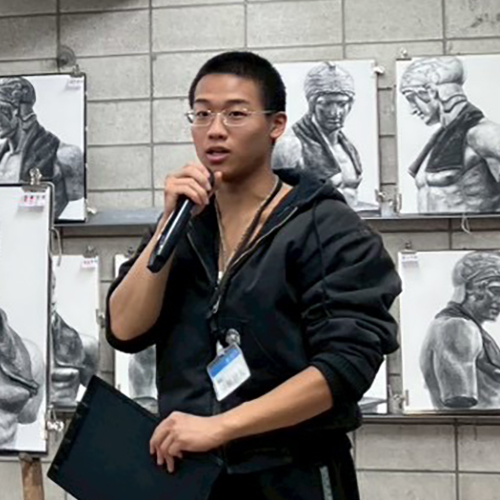
デッサンに対して向き合っている姿勢を全体として感じました。とてもかっこいい姿勢だと思います。毎日デッサンをしているとどんどん些細なことまで気がつけるようになってくるような気がします。素晴らしい成長だと思います。どうやら、些細なことに集中しすぎるともともと気が付いていた事を見過ごしてしまったりもするようです。当たり前とは何か考えながら当たり前なデッサンを書くのも良いかもしれません。